世界的経済学者が説く「揺らぐ資本主義」への処方箋
格差や不平等、気候変動、社会的排除などを生んだ原因として、資本主義が大きな批判を受けている。世界的経済学者のコリン・メイヤー・オックスフォード大学教授の近著『資本主義再興 危機の解決策と新しいかたち』は、この深刻な問題の解決をテーマにしている。同書を監訳した宮島英昭・早稲田大学商学学術院教授に、メイヤー教授が示す資本主義の処方箋について聞いた。(聞き手は沖本健二=日経BOOKSユニット編集委員)
利益とは何か? どこから得られたものか?
今、資本主義に様々な批判が向けられていて、中には、もう資本主義は限界だという主張もあります。『資本主義再興』の著者であるオックスフォード大学のコリン・メイヤー教授は、資本主義のどの部分が問題だと言っているのですか。
宮島英昭氏(以下、宮島) 1973年のオイルショックとその後のスタグフレ―ションの背景として、フリードマン・ドクトリンといわれる新自由主義が台頭してきました。その後、規制緩和や、民営化が推進され、また、貿易・金融面のグローバル化が進展していきました。2000年代初頭ぐらいまでは、こうした市場経済化により世界経済は比較的順調に成長していました。
ところが、2008~09年のリーマン・ショックを機に、市場経済化の徹底が世界にとってよいことなのかという疑問が提示されました。さらに、2010年代になってから、地球温暖化問題や社会的分断、格差問題など、資本主義の「負の部分」が次々と顕在化すると、それまでの揺れ戻しで資本主義批判が強まっていったという経緯があります。
資本主義の父であるアダム・スミスは、『国富論』の中で、個々人が欲望のままに動いても最終的には「神の見えざる手」、つまり市場経済により最適な資源配分が実現されると述べていますが、メイヤーが重視するのは『国富論』の前に書かれた『道徳感情論』です。そこでは利潤の追求の仕方や利益の源泉について、倫理的な観点から詳しく述べられていますが、こうした主張がいつの間にか忘れ去られ「見えざる手」だけが独り歩きしてしまったとメイヤーは指摘しています。
メイヤーは、資本主義がダメだと言っているのではなく、資本主義の原動力である「利益」の概念の再定義を核に資本主義の原理を再構成し、それに沿ってシステムを再構築すれば、自分たちが必要とする形に変えることができると考えています。
宮島英昭(みやじま・ひであき)氏
早稲田大学 常任理事・商学学術院教授。立教大学経済学部卒業、東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得修了、早稲田大学商学博士。東京大学社会科学研究所助手、ハーバード大学ライシャワー研究所客員研究員などを経て現職。財務省財務総合研究所・特別研究官、独立行政法人経済産業研究所(RIETI)ファカルティフェロー、早稲田大学高等研究所所長を歴任。また、経済産業省「コーポレートガバナンスシステム研究会」委員、同「我が国企業による海外M&A研究会」座長、RIETI「企業統治分析のフロンティア」プロジェクトリーダーを務める。(写真:鈴木愛子、以下同)
「利益」の概念をどのように再定義すべきだと主張しているのですか。
宮島 他者の問題を解決して得られる利益を「正当な利益」と定義し、逆に、他者を犠牲にして得られる利益を「不当な利益」として否定しています。企業の目的(パーパス)は単なる利益追求ではなく、利益を伴う形で社会や環境などの地球的な問題までを含めて「他者」の問題を解決することだと主張しています。
ただし、「利益の実現」と「社会的課題の解決」の両立は実は容易ではなく、しばしばトレードオフの関係にある。それをどのように解決していけばよいのかが大きな課題になります。これに対しては、いくつかの方法が考えられます。
例えば、フリードマン的な考え方の人たちは、「株主価値を最大化する上で、経営者は他のステークホルダーや社会的課題に対して可能な限り配慮することで企業の長期的な価値も実現できるので、2つは両立できる」と主張する。これはエンライトメント・キャピタリズム(啓蒙的資本主義)といわれているのですが、メイヤーに言わせれば、目的と手段が逆であり、目的(パーパス)はあくまで他者の問題解決にあるべきだという主張です。
一方、フリードマン的な考え方とは全く逆で、「社会的問題と企業の利潤追求が対立した際、社会的問題の解決を優先して目指しなさい」という意見もある。けれども、企業の善意や利他主義だけでは、一時的には問題が解決されたとしても、持続可能なものにはならない。
メイヤーの提案は、①他者を犠牲にして利益を上げてはいけない、②他者の問題を解決することで利益を上げる、という2つの方向で利益の概念を再構成することです。ここには、利益を得るプロセスで正義に反する行動を取らないという道徳律、企業倫理が組み込まれています。
「外部性」を反映する会計制度が必要
利益には、「正当な利益」と「不当な利益」の2種類あり、後者は利益として認めないという考え方ですね。
宮島 現在は、他人や環境、社会に害を与えて上げた利益が過大に評価され、逆に、社会課題の解決に向けて一生懸命に頑張っている企業の努力が過小評価されて利益に反映されていない傾向にあると、メイヤーは指摘しています。
環境や社会に害を与えて利益を得ている場合、それらに対する修復や原状回復に必要なコスト、つまり「負の外部性」を自社の財務会計に取り込んで利益と相殺すべきなのですが、現在の会計制度ではそれが求められていないため、利益が過大に評価されている面があります。
逆に、企業が環境や社会にプラスの影響を与えている場合、それが現在の会計制度では正当に評価されておらず、企業の利益が過小評価されているとも指摘しています。社会的課題の解決には短期的に利益が上がらないものがたくさんある。企業に積極的に取り組んでもらうためには、そうした「正の外部性」もしっかりと評価してあげる必要がある。
もし、こうしたことが実現していけば、社会的課題の解決と利益の追求は、トレードオフではなく、両立できるようになるというのが、メイヤーのアイデアです。
このアイデアを実現するポイントとなるのは、会社法や会計制度の見直しですか?
宮島 その通りですね。会社法で、企業の目的(パーパス)を「他者の問題を解決して利益を得ること」と明確に位置付け、会計制度では、正当な利益と不当な利益を区分し、後者を認めないようにする。あるいは、負の外部性を内部化するように義務づける。さらに、この2つのほかにも、企業の所有形態や金融のあり方、政府の役割などについても見直す必要があることを強調しています。
例えば、社会的課題の解決には、どうしても利益が出にくいものがあります。そうした課題にも企業が取り組みやすくするため、政府は補助金や税制などを活用して、企業が「正義の行動」を取りやすいように誘導していくことも重要です。
渋沢栄一とコリン・メイヤーの共通点
『資本主義再興』から日本や日本企業が学ぶべき点を教えてください。
宮島 この本では、企業の行き過ぎた利潤追求を議論の出発点にしていますが、日本は米国などに比べて、まだそこまで利潤追求が徹底できていない面があります。例えば、東証株価指数(TOPIX)構成企業の半数近くのPBR(株価純資産倍率)が1倍割れだったり、G7(主要7カ国)の中で労働生産性が最下位だったりという問題を、解決していかなくてはなりません。言ってみれば、欧米の企業からは周回遅れの状態にあり、日本企業は稼ぐ力が弱い。今批判されている資本主義的な原理を徹底することによって生産性や、資本効率を上げられる余地がまだかなりある。
その上で、日本企業は、いまや地球的問題に直面することになったが、それにちゃんと取り組んでいないという批判が他方では強まっている。つまり、日本企業は、現在、両立が容易ではない2つの課題に直面しているという現実をしっかりと認識する必要がある。そうしないと、社会的課題に取り組むことが、利益が低くなっても仕方がないという言い訳に使われ、結局、2つとも改善できずに共倒れになる恐れがあります。
そうした前提を踏まえた上で、この本から日本や日本企業が学ぶべき重要なことは、メイヤーが提案している、利益とは何か、その源泉は何か、会社のパーパスとは何かという哲学に立ち戻ることです。個々の問題は複雑なので、1つの原理ですべてが解決するわけではありませんが、ここで議論されている哲学に立ち戻って、経営者だけでなく、中間管理職、そして企業を所有する機関投資家が、利益の意味とパーパスとの関係を見直すきっかけになってほしいと思っています。
また、本書の解説にも書いたのですが、メイヤーの主張は、渋沢栄一の『論語と算盤』にも通ずるところがあります。明治時代から大正時代にかけて、士農工商の名残で、商業は卑しいものだと思われていましたし、半面、経済人の利益の追求の仕方にも問題が多かった。渋沢は道徳や倫理を経済人に身につけさせて正義の道を歩ませようとした。つまり、大義を持った利益追求を説いたわけです。
一方、コリン・メイヤーはオックスフォード大学出身で、1990年代に同大学にビジネススクールをつくろうとしたのですが、猛反対に遭って、何度も頓挫しそうになった。オックスフォードというのはまさに学問の府で、アカデミックに比べてビジネスの地位がかなり低かったことが背景にあります。その後、サイードビジネススクールを立ち上げることができたのですが、自分自身が直面したビジネスに対する低い評価を変えるために、ビジネスパーソンのマインドを変えて正義に沿った利益追求を目指す教育を実践しようとしました。
ビジネススクールは経営やお金を稼ぐ方法を教えなければなりませんが、企業倫理もしっかり教えて、正しい利潤追求をするビジネスパーソンを輩出し、彼らが正しいビジネスを実践すれば、ビジネスに対する社会からの低い評価も変わっていくだろうということで、これまで奮闘してきたわけです。
時代が少し違いますが、これは渋沢栄一の主張と全く同じなんですね。こうしたメイヤ-の努力の集大成が『資本主義再興』に結実していると思います。
コリン・メイヤー(著)、宮島英昭(監訳)、清水真人・馬場晋一(訳)、日経BP、3300円(税込み)

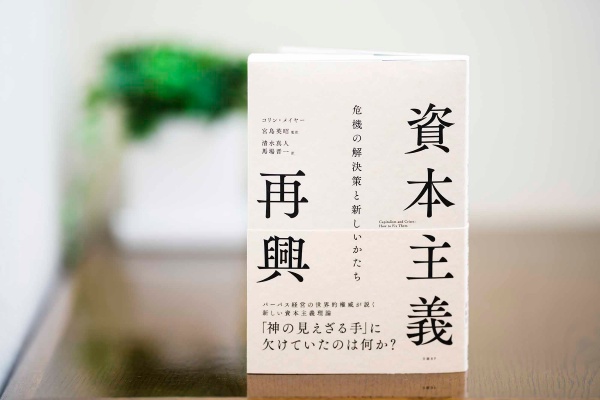

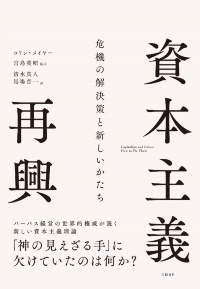



0 件のコメント:
コメントを投稿